加藤雄次郎– Author –
 加藤雄次郎
加藤雄次郎
東京大学在学中に公認会計士試験に合格し、2014年よりKPMGあずさ監査法人に入所、国際事業部にて、日系・外資系企業に対して業務を提供。2017年にKPMGあずさ監査法人退所後、PwC中国に入所し、中国にて事業展開を行う日系企業、及び、日本進出を行う中国企業に対して業務を提供。
2021年にPwC中国を退所後、同年3月に加藤雄次郎公認会計士事務所を設立。
事業拡大に伴い、2022年にLinkard Groupを立ち上げ、代表取締役CEOに就任。
-
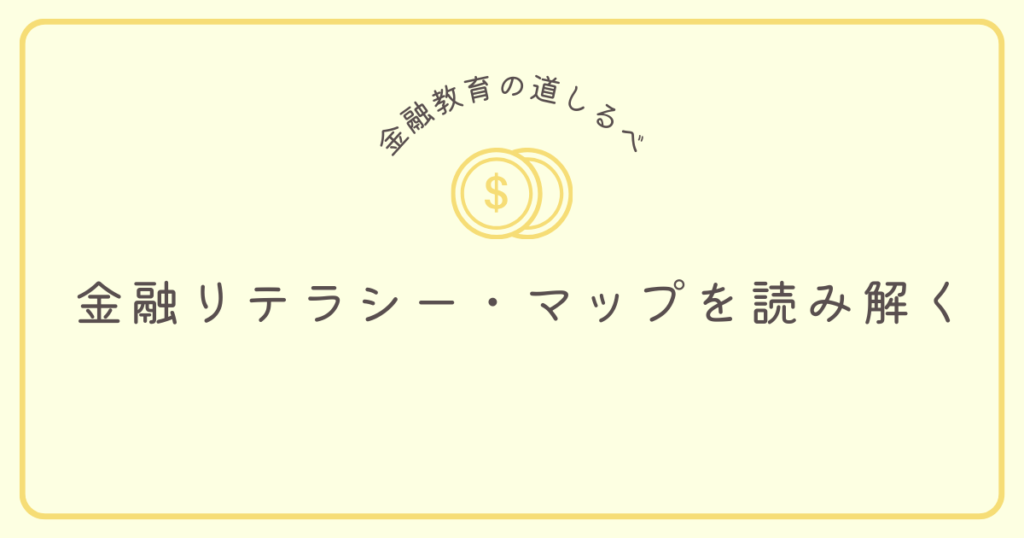
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生中学年編-(第4回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生中学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「金融取引の基本としての素養」の観点から解説しました。 今回は、小学生中学年に求められる金融リテラシーについて「金融分野共... -
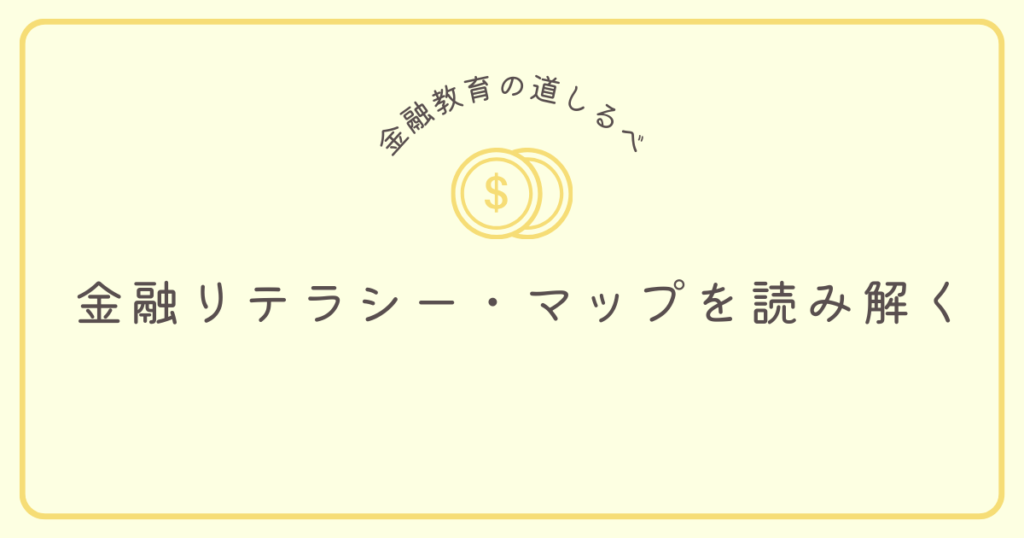
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生中学年編-(第3回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生中学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「生活設計」の観点から解説しました。 今回は、小学生中学年に求められる金融リテラシーについて「金融取引の基本としての素養」の観... -
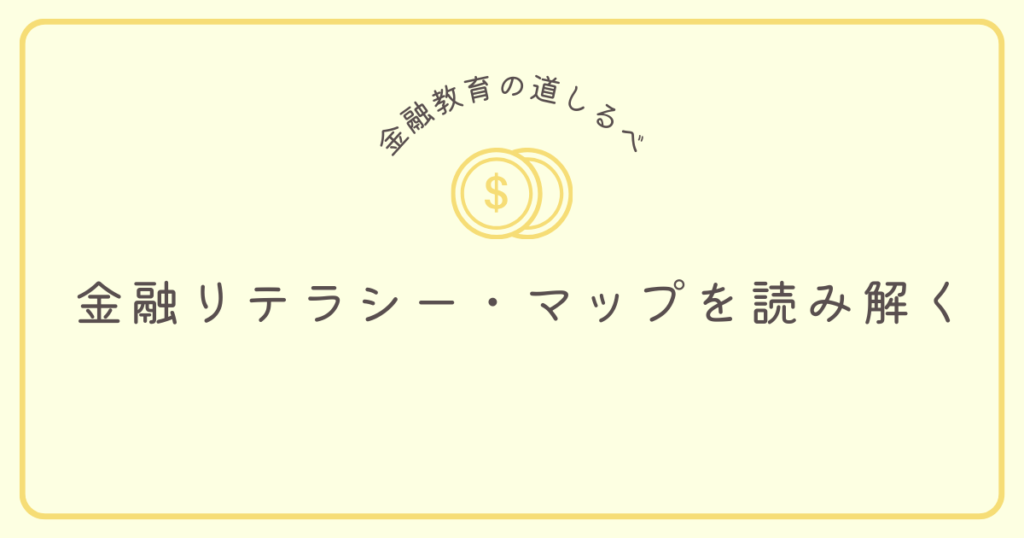
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生中学年編-(第2回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生中学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「家計管理」の観点から解説しました。 今回は、小学生中学年に求められる金融リテラシーについて「生活設計」の観点から解説して... -
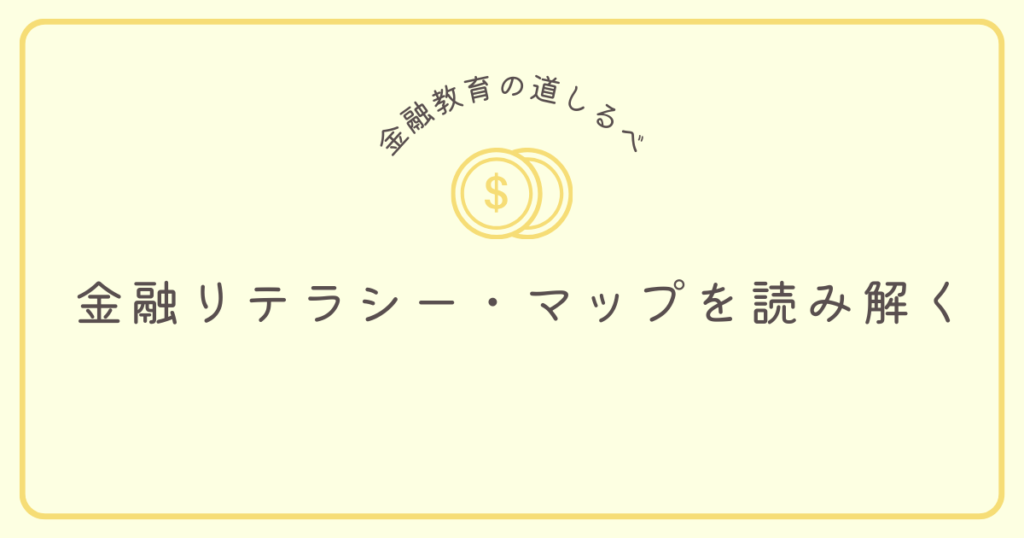
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生中学年編-(第1回)
前回までの記事で金融リテラシー・マップを基に、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて解説してきました。 今回から複数回にわたって、小学生中学年に求められる金融リテラシーについて解説していきます。 家計管理の観点 金融リテラシ... -
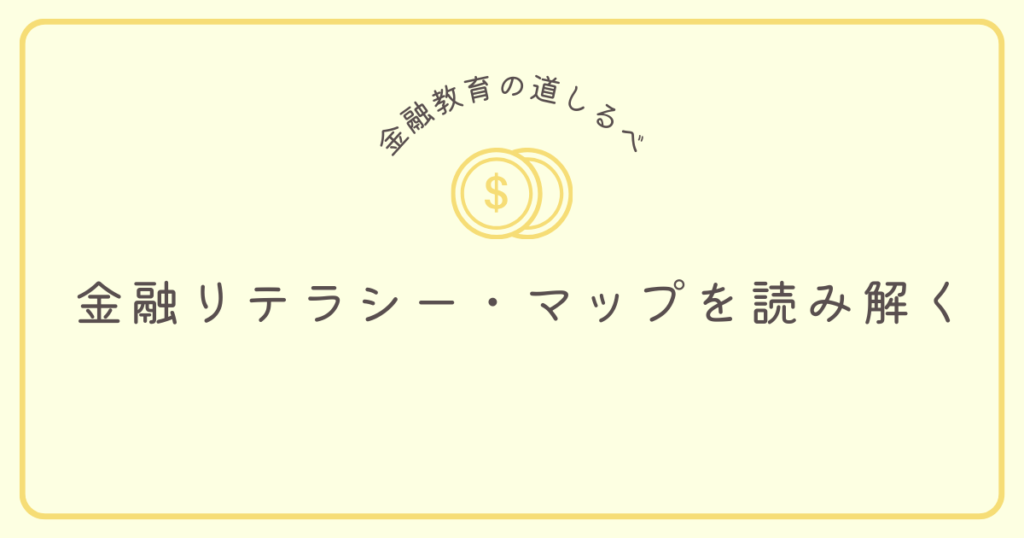
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(最終回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「外部の知見の適切な活用」の観点から解説しました。 今回は、これまでみてきた観点をふまえて、小学生低学年で身に付けたい金融... -
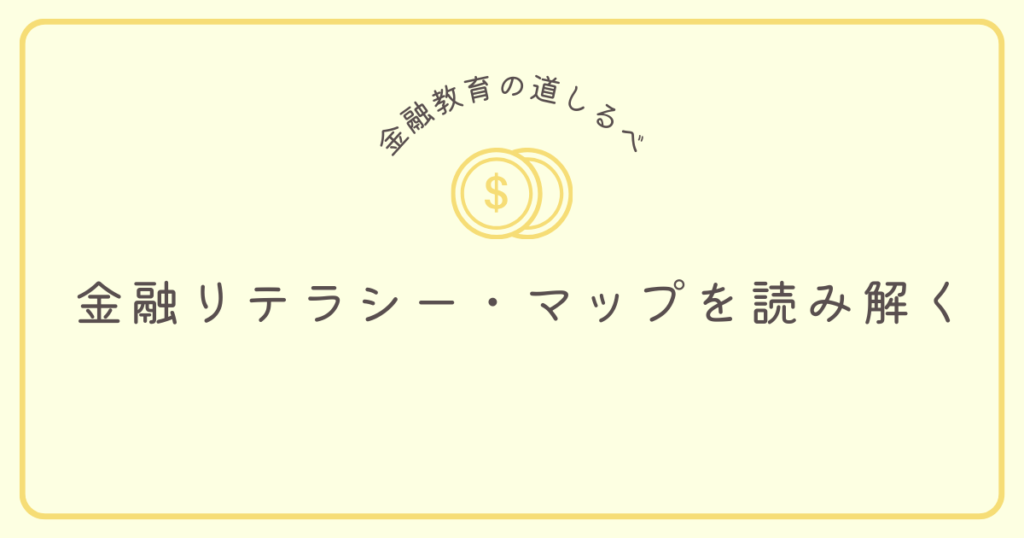
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(第8回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「資産形成商品」の観点から解説しました。 今回は、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて「外部の知見の適切な活用」... -
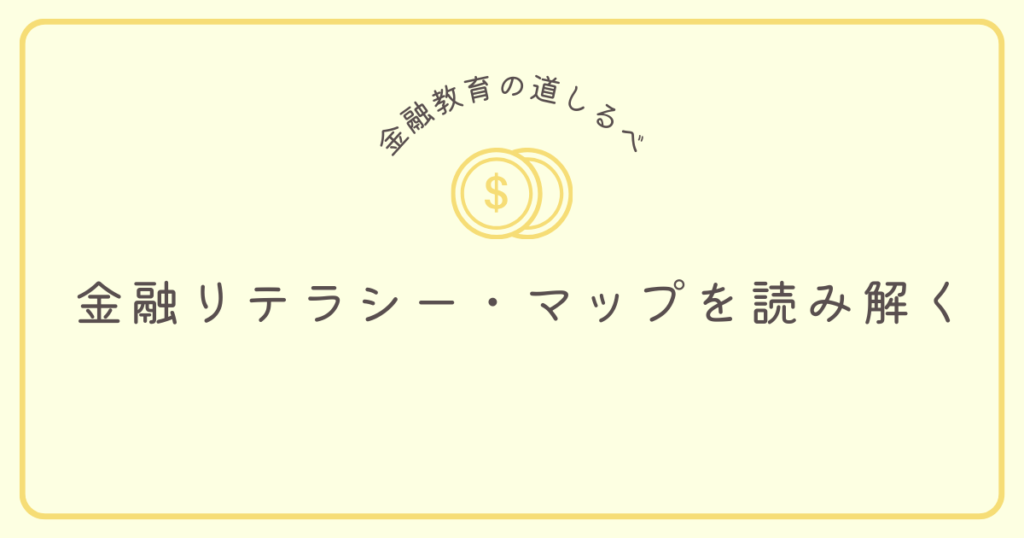
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(第7回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「ローン・クレジット」の観点から解説しました。 今回は、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて「資産形成商品」の観... -
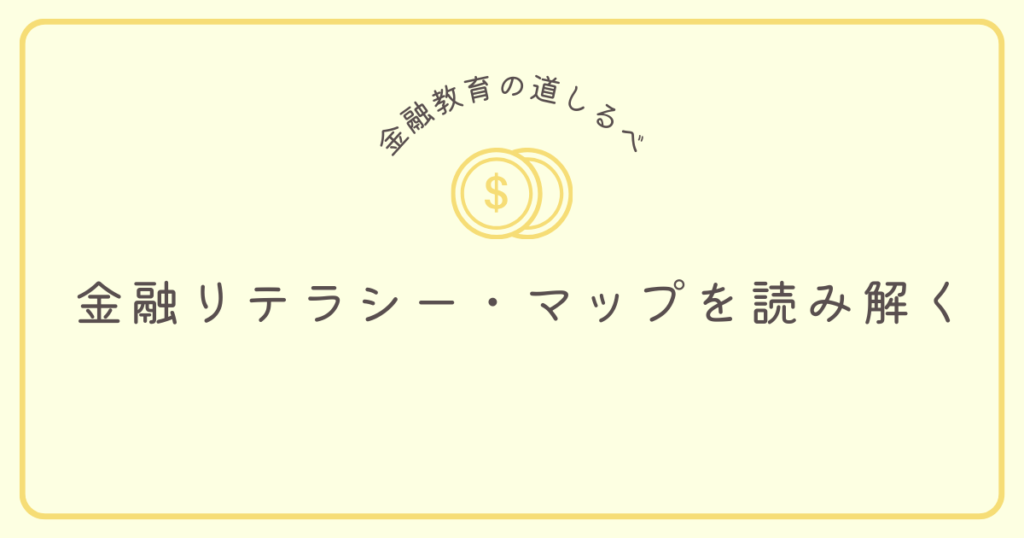
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(第6回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「保険商品」の観点から解説しました。 今回は、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて「ローン・クレジット」の観点か... -
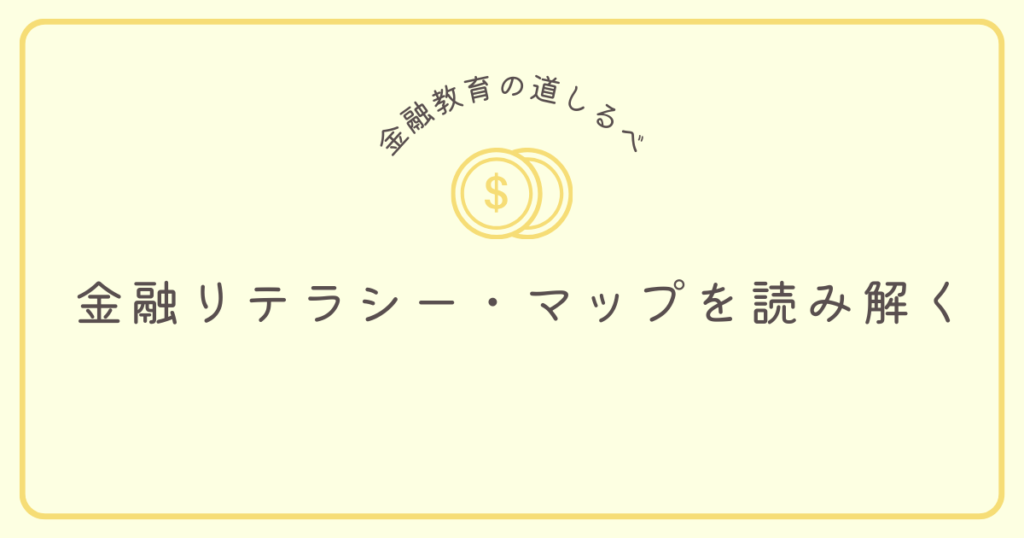
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(第5回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「金融分野共通」の観点から解説しました。 今回は、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて「保険商品」の観点から解説... -
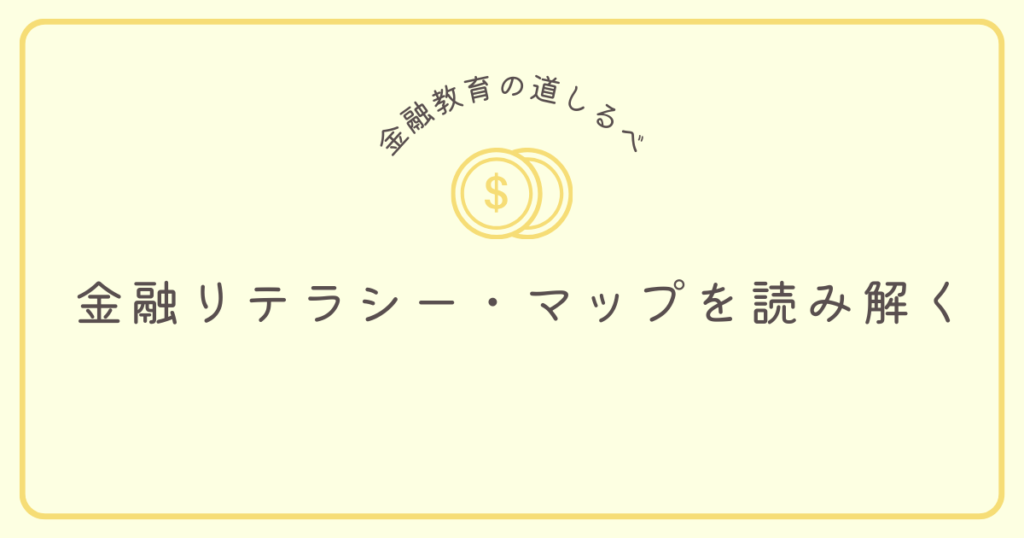
金融リテラシー・マップを読み解く-小学生低学年編-(第4回)
前回の記事で金融リテラシー・マップを横断的な枠組みの1つ、小学生低学年で身に着けるべき金融リテラシーについて、「金融取引の基本としての素養」の観点から解説しました。 今回は、小学生低学年に求められる金融リテラシーについて「金融分野共...
